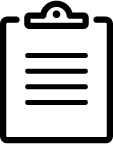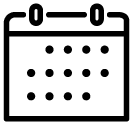二次検査secondary infertility testing
こんな検査が必要<症状に合わせて行う二次検査>
これまでの6大基本検査である程度の不妊原因はわかりますが、その基本検査で何らかの異常が認めたり、不妊治療期間が長期に及んだ場合は、患者さん個人に合わせた次の検査が必要になることがあります。
- 各種のホルモン検査
-
6大基本検査によって排卵障害が認められた場合は、各種のホルモン検査が必要になります。たとえば、卵巣を刺激し、卵胞の発育と排卵を促すには、脳からの各種ホルモンの分泌がなければなりません。また、たとえ分泌されたとしても、分泌量や時期が適当でないと結果として排卵障害につながることがあります。
【ホルモン検査のいろいろ】
- 性腺刺激ホルモンの検査
卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体化ホルモン(LH)を調べます。ちなみに、検査段階においては、月経周期の早い時期(卵胞期初期)にホルモン値を調べることが望ましいとされているので、場合によっては受診されてすぐに検査する場合もあります。 - 卵巣性ホルモンの検査
卵胞ホルモン(エストロゲン)、黄体ホルモン(プロゲステロン)を調べます。 - 男性ホルモンの検査
男性ホルモンの分泌が異常に高レベルになった場合、排卵障害の他、ニキビや肥満の原因になります。また、場合によっては多毛を伴うこともまれにあります。
【よくあるホルモン検査1 LHチェック】
尿中の黄体化ホルモン(LH)の変化を見て排卵日を予測する検査で、自宅で手軽にできる方法です。排卵日を予測することで的確な性交のタイミングを知ることができます。【よくあるホルモン検査2 GnRHテスト】
性腺刺激ホルモン・放出ホルモン(GnRH)を投与して、卵胞刺激ホルモンと黄体化ホルモンを測定し、それぞれのホルモンが正常に分泌されるかを検査します。【よくあるホルモン検査3 乳腺刺激ホルモン】
乳腺刺激ホルモン(プロラクチン)の分泌異常があると、月経の異常や排卵障害が起こります。本来このホルモンは授乳しているときに分泌されますが、何らかの障害で妊娠前の女性に過度に分泌されると生理不順や排卵障害の原因につながります。【よくあるホルモン検査4 抗ミュラー管ホルモン(AMH:Anti-Mullerian Hormone)】
簡単に説明するとこの数値から卵巣にあとどれくらい卵胞が残っているかの指標になります。詳細は用語集を参考にしてください。 - 性腺刺激ホルモンの検査
- 抗精子抗体検査
-
精子の進入が確認できてもその運動性がよくないケースもあります。これは免疫性不妊のところで説明した通り、女性の体内に精子と結合してその働きを阻害する、抗精子抗体という物質を持っている可能性があります。この物質の存在を血液検査にて調べることができます。
- 子宮内膜組織検査
-
基礎体温で高温層が持続する期間は10~14日間程度が理想ですが、その持続期間が10日以下であったり、また、低温層と高温層の格差が小さい場合は、黄体機能不全の疑いがあります。黄体が正常に働かないと子宮内膜が成熟されなかったり、妊娠までの内膜保持が難しくなります。
この場合の直接的な診断法として、耳かきのような器具で子宮内膜の一部を採取し、組織を顕微鏡で観察する子宮内膜組織検査があります。これによって黄体期の子宮内膜として正常な状態にあるのかがわかります。
- 子宮鏡検査
-
子宮卵管造影で、卵管が閉塞していたり子宮腔に異常が認められたときは、膣から内視鏡(ファイバースコープ)を挿入して子宮内を直接テレビモニターで見る子宮鏡検査が必要です。卵管が閉塞していても、ファイバースコープの先端から細い管を出すことで、比較的簡単に通過性を回復できる場合もあります。この様子は、医師と患者さんが同じモニター画面を見ながら行います。また、子宮内にポリープなどが発見された場合は、麻酔をかけて患部を取り除くことも可能です。
この検査は、子宮口を広げる処置が必要なため、前日の夕方から1泊の入院が必要です。
子宮鏡検査

直径数mm程度の細いファイバースコープを膣内から入れ、卵管の入り口の状態を検査する。卵管が閉塞している場合は、細い管を卵管に通すことで通過性を回復できる場合もある。
- 腹腔鏡検査
-
卵管障害(卵管水腫等)による不妊や不妊治療が長期に及んだ場合、その原因を究明する検査として有用で、子宮内膜症診断には欠かせない検査でもあります。また、何度か人工授精を行った人に対しては、その後も同じ治療を続けるか、もしくは体外受精に移行するべきかの判断材料にもなります。実際には、臍下部に直径4mm程度の針を刺し、そこから直径3mm程度の内視鏡をお腹の中に挿入して、子宮、卵管、卵巣を直接観察します。このとき、軽度の癒着や小さな腫瘍などは内視鏡下の手術が可能です。
この検査は開腹は伴いませんが全身麻酔が必要なため、検査としてはそれほど簡単なものではありません。
腹腔鏡検査

内視鏡によって子宮全体を外側から検査すると、卵管采の変形や卵巣の癒着、そして子宮内膜症の有無など不妊原因がより正確に判断できる。
- 精子先体反応検査
-
精子の数や運動率に問題はなくとも、なかなか妊娠できずに不妊治療が長期化している男性患者さんに対しては、より高度な精子検査が必要です。精子が卵子の外側の膜(透明体)を通過するときは、精子の頭部から透明体を溶かすための酵素アクロシンを分泌します。この一連の流れを精子先体反応と呼びますが、アクロシンの濃度が低い場合は卵の中に進入しにくくなってしまいます。精子先体反応検査は、アクロシンの濃度や量を測定し、精子先体の機能を調べるために必要な検査です。
- 精子進入検査(ハムスターテスト)
-
あらかじめ透明体を除去したハムスターの卵子を使って、精子の進入能力を調べる検査です。卵子の中にたくさんの精子が入っているほど、その進入能力が高いといえますが、用意したハムスター卵の30%以上の進入が確認できれば精子に問題はありません。
- 精巣生検
-
精液検査で精子が認められない患者さんに対して行います。精巣(睾丸)の中で精子がきちんとつくられているかどうかを調べるために、精巣組織の一部を採取し、顕微鏡を使って精子の存在や精子細胞の有無を確認します。この手術は、陰嚢(いんのう)の一部を1.5cmほど切開し、マッチ棒の先ほどの小さな組織を採取します。この組織を調べることによって、どの程度成熟した精子があるか、どの程度の精子細胞があるかを正確に判断できます。
当クリニックでは、精子および精子細胞を認めた場合、患者さんの希望があれば採取した精巣組織をすべて凍結保存し、以後の不妊治療に用いています。
実際の手術では、局所麻酔で行うため痛みは伴いません。30分ほどで手術は完了し、その後3時間ほど安静にしていれば当日帰宅できます。なお、手術後約1週間で抜糸となるので再び来院が必要です
- 精路・精嚢造影
-
精子は精巣でつくられ、精管を通って尿道に放出されます。精路・精嚢造影は、精路の障害のため精子が外に出られないという状況を確認するための検査です。一般的な経精管法は、精管のすぐ上の皮膚を1cmほど切開して造影剤を精管内に注入し、その後のレントゲン撮影によって精巣上体から尿道までの精子の通り道を調べます。